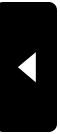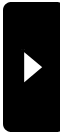くだもの
ポットで簡単!くだもの栽培♪
2013年07月30日
こんにちは、渡辺です
今日は、滋賀県産の果樹栽培を影で支えている研究機関の
ご紹介でしたがいかがでしたか?
今日、取材に伺ったのは 滋賀県農業技術振興センター
花・果樹研究部。
花・果樹研究部は栗東市のJRAトレーニングセンターの近くにあり、
花や果物の栽培技術について試験研究をされています。
例えば花では、水田を利用した小菊栽培やハウスでの草花栽培の方法
だったり、果物だったら品質の良い果実をより早く収穫するために
どうしたらよいか、また、作業の負担軽減するにはどうしたら
よいか・・・などです。
で、今日は近年特に力を入れておられる
誰でも簡単に取り組める果樹のポット栽培についてお話を聞いてきましたよ
お話をしていただいたのは、果樹担当の中井さん

さて、皆さん
いちぢく、柿、桃が木になっているところを想像してみてください。
大きな木に実がなって入る・・・そんなイメージではありませんか?
作業も脚立を使わなとできない、高いところの作業だと
実際そうで、大きな木になりますし、と苗を植えてから収穫できるまで
数年かかってしまうそうです
また一方で、稲作についても想像してください。
稲作をされている方はだいたい、育苗ハウスという
田植え用の稲を育てるハウスを持っていますが、それは田植えまで
のほんの2カ月ほど使用するだけであとは使用しません。
残りの時期、ハウスは???
ハウスの空きを利用して、作業も簡単にできる果樹栽培が
出来ないか?・・・と研究がスタートし、
軽量ポット栽培技術 が開発されたわけです


私の背丈より少し大きいくらいでしょ
軽量ポットなので、移動が簡単。
女性やお年寄りでも作業が出来ます。
さらには空いている空間と時期を利用するので、+αの収入が生まれる訳で
さらにさらに、土に直植えしないので、土壌病害のリスク軽減もはかれ
栄養条件や水の条件がいい為、種類によっては身が大きくなる
果物あるんだそうですーっ
ほんといいことづくしですね
現在は、いちぢくと柿の軽量ポット栽培が実用化し、取組も進んでいるとか。
いちぢくは栽培マニュアルもあるので誰にでも取り組めるそうです。

ブルーベリーと桃は現在、技術確立に向けて研究が進められています。
このほか、ブドウの高品質技術などの研究も。


期待したいですね
センターは研究機関の為、私たちが普段直接接する
ことはあまりありません。
だけど、センターで開発された技術により、生産者さんの裾野拡大に
繋がり、滋賀県産の果物の生産量がアップすれば
私たちも滋賀県産の果物を食べる機会が増えますね。
「技術開発をとおして皆さんと繋がっているんですよ」と
中井さんもおっしゃってました~

研究機関をより身近に感じることができました!
勿論、環境にも配慮。
ポット栽培の土は、JRAから出る馬糞堆肥や滋賀県産の針葉樹のチップを
使い、低価格で資源の循環も意識されているようです。


滋賀県は果物の大きな産地はありませんが、
県内産の果物は直売所を中心に置いています。
地元の恵で育った新鮮な地元の果物を食べることができるのは
幸せなことだと思います。
是非皆さんにも旬を楽しむ、新鮮な果物を食べる幸せを味わってほしいです
また来週の放送もお楽しみに

今日は、滋賀県産の果樹栽培を影で支えている研究機関の
ご紹介でしたがいかがでしたか?
今日、取材に伺ったのは 滋賀県農業技術振興センター
花・果樹研究部。
花・果樹研究部は栗東市のJRAトレーニングセンターの近くにあり、
花や果物の栽培技術について試験研究をされています。
例えば花では、水田を利用した小菊栽培やハウスでの草花栽培の方法
だったり、果物だったら品質の良い果実をより早く収穫するために
どうしたらよいか、また、作業の負担軽減するにはどうしたら
よいか・・・などです。
で、今日は近年特に力を入れておられる
誰でも簡単に取り組める果樹のポット栽培についてお話を聞いてきましたよ

お話をしていただいたのは、果樹担当の中井さん
さて、皆さん
いちぢく、柿、桃が木になっているところを想像してみてください。
大きな木に実がなって入る・・・そんなイメージではありませんか?
作業も脚立を使わなとできない、高いところの作業だと

実際そうで、大きな木になりますし、と苗を植えてから収穫できるまで
数年かかってしまうそうです

また一方で、稲作についても想像してください。
稲作をされている方はだいたい、育苗ハウスという
田植え用の稲を育てるハウスを持っていますが、それは田植えまで
のほんの2カ月ほど使用するだけであとは使用しません。
残りの時期、ハウスは???
ハウスの空きを利用して、作業も簡単にできる果樹栽培が
出来ないか?・・・と研究がスタートし、
軽量ポット栽培技術 が開発されたわけです

私の背丈より少し大きいくらいでしょ

軽量ポットなので、移動が簡単。
女性やお年寄りでも作業が出来ます。
さらには空いている空間と時期を利用するので、+αの収入が生まれる訳で

さらにさらに、土に直植えしないので、土壌病害のリスク軽減もはかれ
栄養条件や水の条件がいい為、種類によっては身が大きくなる
果物あるんだそうですーっ

ほんといいことづくしですね

現在は、いちぢくと柿の軽量ポット栽培が実用化し、取組も進んでいるとか。
いちぢくは栽培マニュアルもあるので誰にでも取り組めるそうです。
ブルーベリーと桃は現在、技術確立に向けて研究が進められています。
このほか、ブドウの高品質技術などの研究も。
期待したいですね

センターは研究機関の為、私たちが普段直接接する
ことはあまりありません。
だけど、センターで開発された技術により、生産者さんの裾野拡大に
繋がり、滋賀県産の果物の生産量がアップすれば
私たちも滋賀県産の果物を食べる機会が増えますね。
「技術開発をとおして皆さんと繋がっているんですよ」と
中井さんもおっしゃってました~

研究機関をより身近に感じることができました!
勿論、環境にも配慮。
ポット栽培の土は、JRAから出る馬糞堆肥や滋賀県産の針葉樹のチップを
使い、低価格で資源の循環も意識されているようです。
滋賀県は果物の大きな産地はありませんが、
県内産の果物は直売所を中心に置いています。
地元の恵で育った新鮮な地元の果物を食べることができるのは
幸せなことだと思います。
是非皆さんにも旬を楽しむ、新鮮な果物を食べる幸せを味わってほしいです

また来週の放送もお楽しみに

タグ :農業技術振興センター栗東市
安土deマンゴー!
2013年07月23日
こんにちは、渡辺です
今日の放送いかがでしたか?
最近、スイーツにもよくよく登場するマンゴ~
そのマンゴーが滋賀でも作られているんですっっ

場所は近江八幡市安土の内野地区。
お話を伺ったのは

(農)内野営農組合法人 代表理事 仙波 謙三さん
マンゴーの品種って主なものだけでも80種類もあるんですよ。
その中で、内野で作られているマンゴーはアーウィンという品種。

マンゴーの生産量は、インド、中国、タイ、パキスタンですが、
日本が多く輸入されているのはメキシコ、フィリピン、タイ、台湾等。
国内の生産量をみると沖縄、宮崎、鹿児島などなど
こうやって見ると温かい地域が多いですよね
じゃあ、どうして安土でマンゴーを??と思ってしまいますが・・・
そもそも、最初からマンゴーを始めよう!とスタートした
わけではありません。
内野地区は、平成18年に集落営農をスタートされましたが、
自立する農業を目指すため、付加価値をつけることが
できる新たな収入源の農作物を探していました。
そんな時に、大学の先生や企業の方等、色んな人との
”つながり”や”縁”が安土にマンゴーをもたらしたわけです
実は、九州と気候が変わらないというのも決め手だったみたいですよ。
マンゴーは、3本の枝から2本の芽を出します。
さらにその2本からまた2本の枝が・・・
なので、次の年は2倍。倍倍で毎年収穫量が増えるんだそうです。
現在は、テスト栽培で168㎡、3年目の今年は550個程収穫できたそうです

しかし残念ながら、今は内野地区の住民を優先に販売しているため
ほとんど市場には出ていません
------------
内野のマンゴーは環境にも優しい栽培しているんですよっ
重油の使用を減らしヒートポンプを使用、
農薬は極力減らし、有機肥料による栽培など

黄色と青色の短冊みたいのは補虫シート。
そんなマンゴーは今が旬

真っ赤に鮮やかになったマンゴーは収穫時期になると
自らポロっと枝から落ちます。
なので、1個1個ネットに入っていて落ちるのを防いでいるんですね
では、最後に
仙波さんに今後の夢をお聞きしました

「夢は滋賀県全体に生産者を増やして若者が地元で働ける場をつくること、
お年寄りも生きがいとなる農業を広げること、
そして、内野で作っているマンゴーを”びわマンゴー”として
ブランド化して量産すること」
近い将来、びわマンゴーが滋賀の特産となって身近に滋賀県産
マンゴーが食べられる日が来るのを楽しみにしていますね
元気な「滋賀の農業」広め隊 来週もお楽しみに

今日の放送いかがでしたか?
最近、スイーツにもよくよく登場するマンゴ~

そのマンゴーが滋賀でも作られているんですっっ

場所は近江八幡市安土の内野地区。
お話を伺ったのは
(農)内野営農組合法人 代表理事 仙波 謙三さん
マンゴーの品種って主なものだけでも80種類もあるんですよ。
その中で、内野で作られているマンゴーはアーウィンという品種。
マンゴーの生産量は、インド、中国、タイ、パキスタンですが、
日本が多く輸入されているのはメキシコ、フィリピン、タイ、台湾等。
国内の生産量をみると沖縄、宮崎、鹿児島などなど
こうやって見ると温かい地域が多いですよね

じゃあ、どうして安土でマンゴーを??と思ってしまいますが・・・

そもそも、最初からマンゴーを始めよう!とスタートした
わけではありません。
内野地区は、平成18年に集落営農をスタートされましたが、
自立する農業を目指すため、付加価値をつけることが
できる新たな収入源の農作物を探していました。
そんな時に、大学の先生や企業の方等、色んな人との
”つながり”や”縁”が安土にマンゴーをもたらしたわけです

実は、九州と気候が変わらないというのも決め手だったみたいですよ。
マンゴーは、3本の枝から2本の芽を出します。
さらにその2本からまた2本の枝が・・・
なので、次の年は2倍。倍倍で毎年収穫量が増えるんだそうです。
現在は、テスト栽培で168㎡、3年目の今年は550個程収穫できたそうです


しかし残念ながら、今は内野地区の住民を優先に販売しているため
ほとんど市場には出ていません

------------
内野のマンゴーは環境にも優しい栽培しているんですよっ

重油の使用を減らしヒートポンプを使用、
農薬は極力減らし、有機肥料による栽培など

黄色と青色の短冊みたいのは補虫シート。
そんなマンゴーは今が旬

真っ赤に鮮やかになったマンゴーは収穫時期になると
自らポロっと枝から落ちます。
なので、1個1個ネットに入っていて落ちるのを防いでいるんですね

では、最後に
仙波さんに今後の夢をお聞きしました

「夢は滋賀県全体に生産者を増やして若者が地元で働ける場をつくること、
お年寄りも生きがいとなる農業を広げること、
そして、内野で作っているマンゴーを”びわマンゴー”として
ブランド化して量産すること」
近い将来、びわマンゴーが滋賀の特産となって身近に滋賀県産
マンゴーが食べられる日が来るのを楽しみにしていますね

元気な「滋賀の農業」広め隊 来週もお楽しみに

安曇川のアドベリ~
2013年07月08日
こんちわ!隊員の森ちゃんですよ

本日のOAは安曇川のアドベリーでした。

現在は合併し高島市となっている旧安曇川町。浜大津から湖西バイパスで1時間チョイ。JR湖西線の【新快速敦賀行き】なら(ならというかコレでしか行けませんが)山科から乗り換えなし 40分で到着でっす
40分で到着でっす 思ってたより近いでしょ
思ってたより近いでしょ

7年前にオープンした道の駅『藤樹の里あどがわ』は、全国でも指折りのゴキゲンな施設

(高島市HP参照)
僕も何度も行ってますが、福井県との物流の主要道路なのでかなり充実してる大きな道の駅ですよ^^
で、(でってすいません)お話を伺ったアドベリー生産協議会、会長の永田さん。
道の駅『藤樹の里あどがわ』で安曇川の特産品として激オシ販売中なんですよ


何か特産物を作ろうということで、会発足当時から中心となって活動され、
安曇川といえばアドベリーと言われるようがんばりたい!と。
ニュージーランドからボイズンベリーという種類の苗を輸入し、安曇川で栽培。
みなさんご察知の通り、ネーミングの由来でございます。

滋賀県の環境こだわり農産物の認定をうけてらっしゃいます。
が
さらにさらに高島地域独自の農産物規定も、最上級の認定も受けてらっしゃいますよ。すごいッス


(高島市HP参照)
さてさてこのアドベリー、インタビューにもありましたように、木いちごの仲間で自然では這うように育ちます。茎にはバラのようなトゲがいっぱい 容易に手を伸ばすとめっちゃ刺さります。
容易に手を伸ばすとめっちゃ刺さります。
 ハウスでは収穫しやすいよう、花がさく頃までに縦に起して育てます。1株の寿命が7~8年!1シーズンで4~5kg収穫できるそうですよ。
ハウスでは収穫しやすいよう、花がさく頃までに縦に起して育てます。1株の寿命が7~8年!1シーズンで4~5kg収穫できるそうですよ。

栽培されるハウスでは側面を開けてあるとはいえかなりの暑さ


午前中になんとか収穫を終わらせないと、とても体力が持たない、と永田さん。協議会のメンバーやマダムたちと手分けして収穫
これからは農家さんにとっては厳しい季節ですよね くれぐれもお気をつけて
くれぐれもお気をつけて
収穫したアドベリー、そのままでは日持ちしないクダモノだそうですぐに冷凍、もしくは加工品へ使用されます。
アドベリーの加工品はすごくいっぱいあってどれを買うか迷ってしまうほど
商品をご紹介しているキレイなブログをみつけましたので画像とリンク先をのっけときますょん

うめさんのブログ『きょのうめ』http://ameblo.jp/adoume/theme3-10015469938.html
生産協議会では少しでもアドベリーに関心を持ってもらおうと、アドベリーを使ったレシピを公募しており、採用の場合は認定書の発行や道の駅での販売等を行っているそうですよ。
また希望者には家庭菜園用に苗をお譲りすることもされていて、アドベリーの認知度拡大に向けて様々な活動を行っておられます

永田さんらが極めた栽培マニュアルもありますので、アドベリー、ひとつ始めてみませんかぁ



本日のOAは安曇川のアドベリーでした。
現在は合併し高島市となっている旧安曇川町。浜大津から湖西バイパスで1時間チョイ。JR湖西線の【新快速敦賀行き】なら(ならというかコレでしか行けませんが)山科から乗り換えなし
 40分で到着でっす
40分で到着でっす 思ってたより近いでしょ
思ってたより近いでしょ

7年前にオープンした道の駅『藤樹の里あどがわ』は、全国でも指折りのゴキゲンな施設


(高島市HP参照)
僕も何度も行ってますが、福井県との物流の主要道路なのでかなり充実してる大きな道の駅ですよ^^
で、(でってすいません)お話を伺ったアドベリー生産協議会、会長の永田さん。
道の駅『藤樹の里あどがわ』で安曇川の特産品として激オシ販売中なんですよ

何か特産物を作ろうということで、会発足当時から中心となって活動され、
安曇川といえばアドベリーと言われるようがんばりたい!と。
ニュージーランドからボイズンベリーという種類の苗を輸入し、安曇川で栽培。
みなさんご察知の通り、ネーミングの由来でございます。
滋賀県の環境こだわり農産物の認定をうけてらっしゃいます。

が

さらにさらに高島地域独自の農産物規定も、最上級の認定も受けてらっしゃいますよ。すごいッス



(高島市HP参照)
さてさてこのアドベリー、インタビューにもありましたように、木いちごの仲間で自然では這うように育ちます。茎にはバラのようなトゲがいっぱい
 容易に手を伸ばすとめっちゃ刺さります。
容易に手を伸ばすとめっちゃ刺さります。
 ハウスでは収穫しやすいよう、花がさく頃までに縦に起して育てます。1株の寿命が7~8年!1シーズンで4~5kg収穫できるそうですよ。
ハウスでは収穫しやすいよう、花がさく頃までに縦に起して育てます。1株の寿命が7~8年!1シーズンで4~5kg収穫できるそうですよ。栽培されるハウスでは側面を開けてあるとはいえかなりの暑さ



午前中になんとか収穫を終わらせないと、とても体力が持たない、と永田さん。協議会のメンバーやマダムたちと手分けして収穫

これからは農家さんにとっては厳しい季節ですよね
 くれぐれもお気をつけて
くれぐれもお気をつけて
収穫したアドベリー、そのままでは日持ちしないクダモノだそうですぐに冷凍、もしくは加工品へ使用されます。
アドベリーの加工品はすごくいっぱいあってどれを買うか迷ってしまうほど

商品をご紹介しているキレイなブログをみつけましたので画像とリンク先をのっけときますょん

うめさんのブログ『きょのうめ』http://ameblo.jp/adoume/theme3-10015469938.html
生産協議会では少しでもアドベリーに関心を持ってもらおうと、アドベリーを使ったレシピを公募しており、採用の場合は認定書の発行や道の駅での販売等を行っているそうですよ。
また希望者には家庭菜園用に苗をお譲りすることもされていて、アドベリーの認知度拡大に向けて様々な活動を行っておられます


永田さんらが極めた栽培マニュアルもありますので、アドベリー、ひとつ始めてみませんかぁ


安曇川のアドベリー♪♪
2013年06月29日
はいはい~ 隊員の森ちゃんです
7月8日OAは安曇川のアドベリーのご紹介っす


あまずっぱ~いアドベリー、安曇川の道の駅『藤樹の里』で明日30日 アドベリー収穫祭が開催されますよ(^o^)
アドベリー収穫祭が開催されますよ(^o^)
詳しくはコチラから
 http://mitinoeki-adogawa.com/shisetu.html
http://mitinoeki-adogawa.com/shisetu.html

7月8日OAは安曇川のアドベリーのご紹介っす


あまずっぱ~いアドベリー、安曇川の道の駅『藤樹の里』で明日30日
 アドベリー収穫祭が開催されますよ(^o^)
アドベリー収穫祭が開催されますよ(^o^)詳しくはコチラから

 http://mitinoeki-adogawa.com/shisetu.html
http://mitinoeki-adogawa.com/shisetu.html タグ :高島市
滋賀県産メロンは今が旬!!
2013年06月25日
こんにちは、渡辺です
今日は滋賀県産メロンをご紹介しましたがいかがでしたか。
浜街道を1本琵琶湖側に入った草津市北山田から守山まで
まっすぐ道が繋がっています。
これが、 メロン街道 です。

メロン街道の周辺は滋賀県産メロンの産地なんです。。
今日はこの産地で栽培されているメロンについて取材してきました。
まずは 草津メロン
お話を伺ったのは 湖南中央園芸組合メロン部会 部会長 中島 光弘さん


メロン生産10年のベテランです
湖南中央園芸組合メロン部会は現在26名。栽培面積は4.9ha
果肉が緑色のアムスメロン、タカミメロン、センチュリーメロンの3種と
赤色のホノカメロン、タカミレッド、レノンサマーの3種
合計6種類を生産されています。
以前はもっと品種が多かったとか。草津の風土にあう品種は
どんなものか、現在も部会のメンバーで試行錯誤試作されている
そうです。
草津メロンの特徴は、とっても甘いということ
糖度14・6以上を出荷基準にしています。

これは甘さをはかる糖度計
続いてハウスも見学させてもらいました


品質を保つために1株で3つに絞りこむそうです。
「今年のメロンは空梅雨のおかげでとっても甘く自信作!」だそうですよっ
さてさて、メロン街道を北上して次の取材先へ

次はモリヤマメロン
お話を伺ったのは JAおうみ冨士モリヤマメロン部会 部長 浜口 耕一さん

私の左の方です。こちらもメロン栽培14年のベテラン
モリヤマメロン部会員は現在30名 栽培面積は4.9ha。
アムスメロンが90%、他アールスメロン、盆前メロンを生産されています。
モリヤマメロンは約36年前から栽培が始まったのですが、
段々生産者が高齢化、人数が減って来ているそうです。
なので、今年から、後継者育成として
トレーニングハウスを設置して、新規就農者に栽培技術を
伝えています。浜口さんたち部会メンバーも栽培の合間をみて
技術伝承されています。

そんなモリヤマメロンも今が出荷のピークっ
取材の日も関係者皆さん、汗だくになりながら
出荷準備に追われていました


こちらモリヤマメロンも甘くておいしい!と浜口さんの太鼓判。
------------------
メロンの栽培は、非常に手間がかかります。
1株で大量にも取れません
ハウスでの作業は非常に暑く、大変な作業なんです・・・・
でも、皆さんに美味しいメロンを届けたい、
みんなに美味しいと言ってもらうのが励みとお二人は
言われました
これは、生産者皆さんの想いなんだろうなぁと感じました。
私達も、生産者さんに感謝しながら
県内産のメロン食べたいですね!
それではまた来週にお会いしましょう

今日は滋賀県産メロンをご紹介しましたがいかがでしたか。
浜街道を1本琵琶湖側に入った草津市北山田から守山まで
まっすぐ道が繋がっています。
これが、 メロン街道 です。
メロン街道の周辺は滋賀県産メロンの産地なんです。。
今日はこの産地で栽培されているメロンについて取材してきました。
まずは 草津メロン

お話を伺ったのは 湖南中央園芸組合メロン部会 部会長 中島 光弘さん
メロン生産10年のベテランです

湖南中央園芸組合メロン部会は現在26名。栽培面積は4.9ha
果肉が緑色のアムスメロン、タカミメロン、センチュリーメロンの3種と
赤色のホノカメロン、タカミレッド、レノンサマーの3種
合計6種類を生産されています。
以前はもっと品種が多かったとか。草津の風土にあう品種は
どんなものか、現在も部会のメンバーで試行錯誤試作されている
そうです。
草津メロンの特徴は、とっても甘いということ
糖度14・6以上を出荷基準にしています。
これは甘さをはかる糖度計
続いてハウスも見学させてもらいました

品質を保つために1株で3つに絞りこむそうです。
「今年のメロンは空梅雨のおかげでとっても甘く自信作!」だそうですよっ

さてさて、メロン街道を北上して次の取材先へ


次はモリヤマメロン

お話を伺ったのは JAおうみ冨士モリヤマメロン部会 部長 浜口 耕一さん
私の左の方です。こちらもメロン栽培14年のベテラン
モリヤマメロン部会員は現在30名 栽培面積は4.9ha。
アムスメロンが90%、他アールスメロン、盆前メロンを生産されています。
モリヤマメロンは約36年前から栽培が始まったのですが、
段々生産者が高齢化、人数が減って来ているそうです。
なので、今年から、後継者育成として
トレーニングハウスを設置して、新規就農者に栽培技術を
伝えています。浜口さんたち部会メンバーも栽培の合間をみて
技術伝承されています。
そんなモリヤマメロンも今が出荷のピークっ

取材の日も関係者皆さん、汗だくになりながら
出荷準備に追われていました
こちらモリヤマメロンも甘くておいしい!と浜口さんの太鼓判。
------------------
メロンの栽培は、非常に手間がかかります。
1株で大量にも取れません

ハウスでの作業は非常に暑く、大変な作業なんです・・・・
でも、皆さんに美味しいメロンを届けたい、
みんなに美味しいと言ってもらうのが励みとお二人は
言われました

これは、生産者皆さんの想いなんだろうなぁと感じました。
私達も、生産者さんに感謝しながら
県内産のメロン食べたいですね!
それではまた来週にお会いしましょう